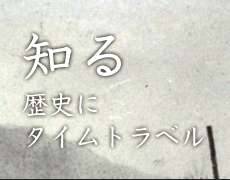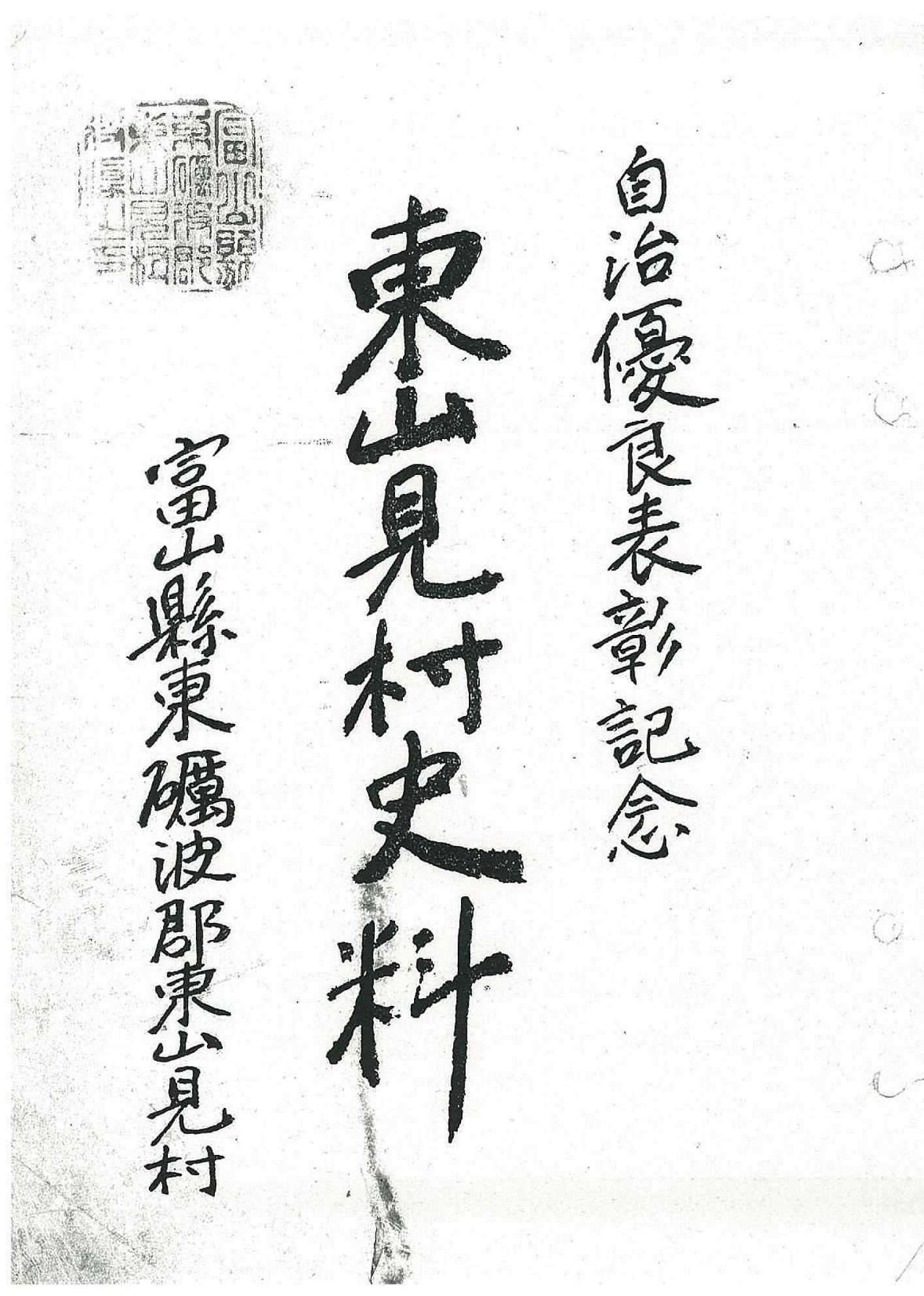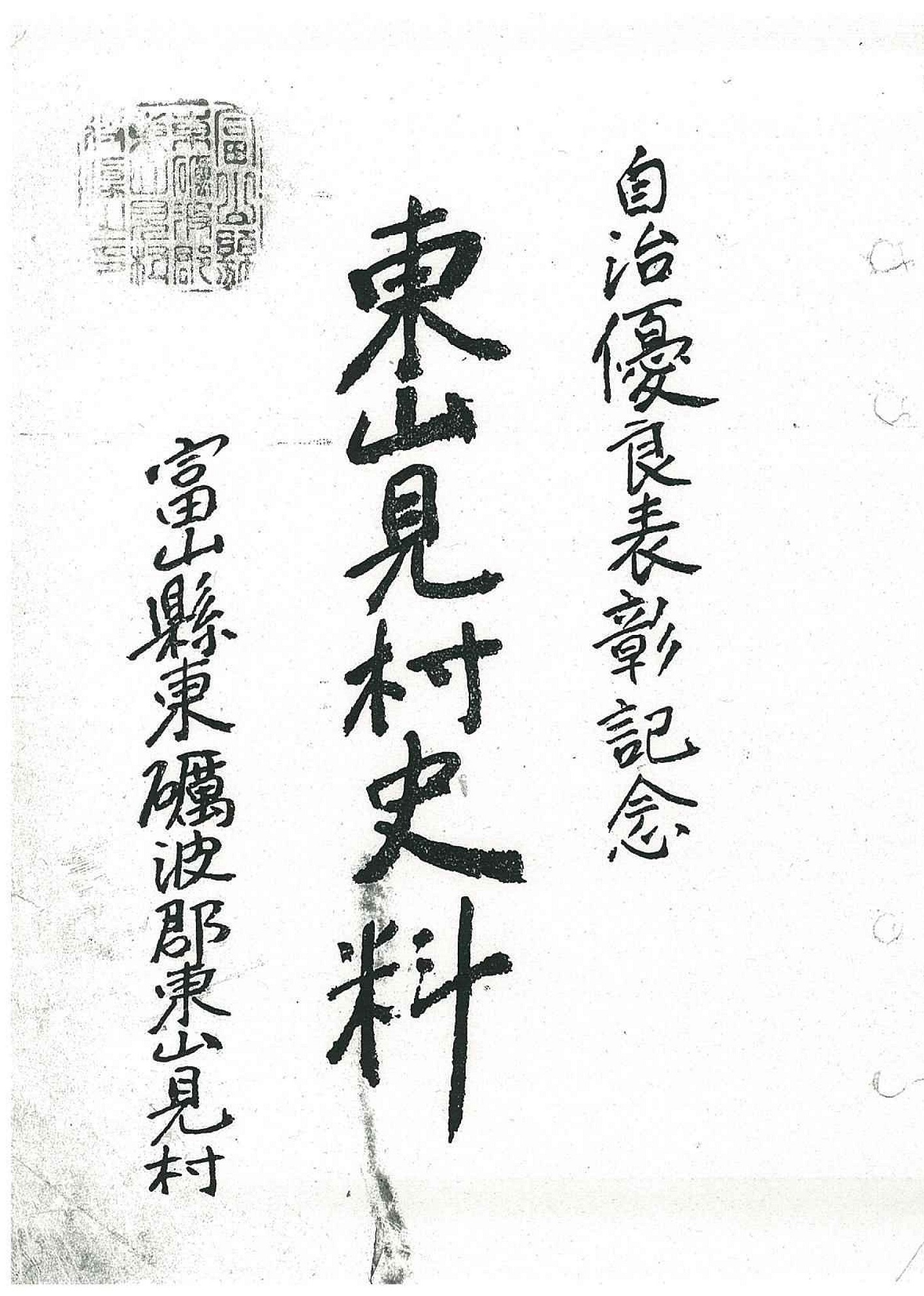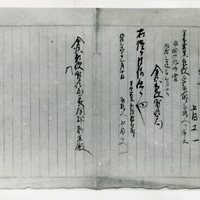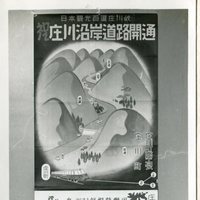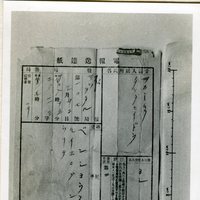�P���쒬�̂����ڂ́i���̂R�j
2016.4.7
�Q�Y�_��i����j�ƌÑ㕶��
���n����Ñ�Љ�
�@�ꕶ����i�����j�Ɋ����w����тƁx�͂��̌�ǂ������̂��B�ꕶ����̎��ɖ퐶����A���ɌÕ����オ����Ă���B���Ȃ킿�Ñ�ւƗ��j���傫���ڂ�킯�ł���B����k�삪�͂��܂�A�S�E���Ȃǂ̋����킪�嗤����A�����ꂽ�퐶����́A��Q�C�R�O�O�N�O�iB.C.�R���I�j����P�C�V�O�O�N�O�iA.D.�R���I�j�܂łÂ����B�@����k�삪���B����ƁA�k��ɓK�����y�n���x�z���錠�͎҂�������A��������悤�ɂȂ����B���߂͏����ȕ������Ƃł��������A�₪�Ď�p�I�Ȍ��n�@���̌��Ђ═�́A���邢�͓S�⓺�Ȃǂ̓Ɛ�ɂ���ċ��͂ȓ���x�z�҂��������悤�ɂȂ����B���ꂪ�Õ�����ŁA�Õ��͂��̂悤�Ȍ��͎҂̃V���{���Ƃ��ėp����ꂽ�̂ł���B�Õ�����R���I������U���I�����܂łÂ������A���̒��S�͑�a�i��܂Ɓj�~�n�i�ޗnj��j��͓��i���킿�j�i���{�j�ȂNjߋE�n���ł������B���쒬��ɂ����̖퐶�E�Õ�������̈�Ղ͌��݂܂Ŕ�������Ă��Ȃ����A���́w����тƁx���A�ǂ��������Ă����̂��낤���B
�@���{�̌Ñ�j�ɑ���S�́A�ߔN�Ƃ݂ɍ��܂�A����“�Ñ�j�u�[��”�ȂǂƂ�����قǂł���B���X�ɌÑ�j�W�̘_�����o�ł���A�V�������������낢��Ȋp�x�����o����Ă���B���̂悤�ȏł���Ȃ���A�����ɂS���I�݂̂Ȃ炸�A�T���I�ɂ��Ă��^�������炩�ɂ��ꂸ“��̐��I”�Ƃ����Ă��錻���ł���B
�@�Ñ�j�̌����ɁA�L�^�E�������邢�͖؊ȁi��������E�����̏����ꂽ�؎D�j�E���Ε��i�����Ԃ�E�����̔��邢�͐ނȂǂɋL���ꂽ���Ȃǂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ͂����܂ł��Ȃ����A�Ƃ��낪�S���I�̂킪���ł͕���������ꂽ���Ƃ𗧏ł��Ȃ����肩�A�T���I�ɂ����Ă������g�p�̊m���Ȃ��̂͏��Ȃ��B
�@�w�Î��L�x��w���{���I�x�ɂ́A�Ȃ�قǁu�_��i���݂�j�v�ȗ��̗��j���L�^����Ă���̂������̗����̊����͂W���I�͂��߁i�ޗǎ���j�ł����āA4�A�T���I�̂��Ƃ����邳��Ă��Ă��A��������̂܂܂��݂̂ɂ���킯�ɂ͂����Ȃ��B���ꂱ���u�_�b�W�v�Ƃ�����䂦��ł���B���̐_�b�̑傫�ȓ��F�͍c���̑c��_�Ƃ���V�Ƒ�_�i�A�}�e���X�I�z�~�J�~�j�𒆐S�Ƃ������V���i�͂����܂��͂�j�̐��E���ڍׂɕ`���āA�c�c�_�̎q���������i�����͂�j�̒����ɓV�~��A���̍��y�肷�邱�Ƃɗ͓_�������Ă���Ƃ���ɂ���B
�@���̂悤�Ɂw�Î��L�x��w���{���I�x�ɂ́A�V���I�㔼����W���I�͂��߂ɂ����ẮA���삨��ѐ��{�̕ҏW�ړI���w�i�Ƃ��đ��݂��Ă���A���͎҂̗���Ɋ�Â��`���̐�������ρA���F��������Ȃ���Ă���Ƃ�����B�����̐_�b�ɑ��āA�悤�₭���ꍑ�ƂƂ��Ắu�הn�䍑�i��܂��������j�v�A�����ď����u�ږ�āi�Ђ݂��j�v�Ȃǂ��A�l�Êw�゠�邢�͒����j���w�`�l�`�i�킶��ł�j�x�Ȃ��ɕ��サ�Ă���̂́A�ߐ��ɂȂ��Ă���ŁA�����̘_���́A�ߔN���Ɋ����ɂȂ��Ă���B
�@
�z�m���Ɠn���l
�@���{�C�̍r�g���ł��鉈�ݒn�тɂ����āA�ߍ]�i�����݁j����k�̖k���n�����A�Â�����u�z�����u�v�Ƃ�ꂽ�B�z�́A��ɉz�O�E�z���E�z��̍��ɕ��������B�z�͏d�v�Ȗ������ʂ����Ă����B���̈�͍��ƓI���ƂȂǂ̘J���͂̋������Ƃ��āA����͉ڈi�����j��̋��_�A�⋋��n�Ƃ��Ăł������B�@�������A�w�Î��L�x��w���{���I�x�ɕ`���ꂽ�z�̃C���[�W�́A�n���I�ɂ������I�ɂ���̃x�[���ɂ܂ꂽ�����������A����́A�������{�ɂ�鐪���E����E�Ď@�Ƃ������������͂ɂ��n���̎x�z�ߒ��𒆐S�ɂ����Ă���B����ɂ��A�z�̍��ɒ����̖��߂ɕ��]������R���������l�X�̑��݂����l�q���m���A���̒������g���Ƃ����g�҂��R���͂��Ƃ��Ȃ��ĉz�։������`�Ղ�������Ă���B
�@����A�����I���i�����łȂ��A�w�Î��L�x�ɕ`���ꂽ�卑�喽�i�I�I�N�j�k�V���~�R�g�j�̋����`���̂悤�ɁA�z�n���Əo�_�n���i�������j�̌𗬂��������킹�郍�}���ɕx���������B���̗ޘb�́w�o�_���y�L�i�V�R�R�N�����j�x�ɂ��݂��A���̏o�_�̑卑�喽�Ɖz�̏��͔䔄�i�k�J���q���j�Ƃ̕���̔w�i�ɂ́A�o�_�n���Ɩk���n���̊Ԃɐ����I�A�o�ϓI�Ȍ𗬂�������Ă�������𐄎@���邱�Ƃ��ł���B
�@����A�ʂ̊p�x����z�̍���K�ꂽ�n���l�ɂ��Ă݂Ă݂悤�B�w���{���I�x�́u�唪�F�i�����₵�܁j�����v�̏��ɂ݂����F�i�������܁j�̏F�́A�V�}�Ɠǂނ��A�N�j�̔����łȂ���Ȃ�Ȃ��B�z�F�̓R�V�m�V�}�łȂ��R�V�m�N�j�ł���A�܂������łƂ肠���Ă����F�̓I�z�̍��Ɠǂނׂ��ł���B�ł̓I�z�̍��Ƃ͂ǂ����B�����܂ł��Ȃ��_�b�̂Ȃ��Ŋ���卑�喽�̖{���A�o�_�n���������Ă���B��������F�ł��������Ƃ́A�o�_�n���ɍ����u��i�I�z�j�v�Ƃ����n�����������Ƃł�������悤�B
�@�卑�喽���܂�푰�́A���Ƃ���o�_�ɂ����̂��B�����炭�k��B���܂ގR�A�����n���ɐ��͂������A���ɂ́A��B���i����i�����j�j�n���ɂ������n���������Ƒz�������B���̃I�z���̂��̌�̈ړ��ɂ��āA����ɑz���W�����Ă݂悤�B
�@�S�핶�������k�������̒��N����̓쉺�ɁA�I�z���͍��������ē��ցA���ւƈړ������B�܂��ꑰ�͏o�_�n���ɌÑ�Љ������Ɋg�����A�ʂ̕��h�͒����R���������ĉ��R�̋g���i���сj�n���ɐi�o���A�₪�Đ��˓����[�g����͓��i���{�j�ɏ㗤���Ă䂭�B������Ñ��a�Љ�̌`���ƂȂ邪�A����A�o�_�̕����́A�Δn�i���܁j�C���ɂ̂��ĒO��i���j�n���ɏ��e�̌�A���{�C���݂𓌂ֈڂ��Ă䂭�B�₪�Ĕ\�o�����ɂ�������A�x�R�p�ɂȂ��ė���̂ł���B
�@����ł̓I�z�̍����������w�I�z�x���Ƃ͉����B�����܂ł��Ȃ��C�Ɋ����`�l�i�����l�Ȃǂ����{�l���ĂḮj�̈ꕔ�Ƃ����Ă���B���������`�l�̓����́A�퐶�����ƌ������N��łȂ��A����ȑO�̋v�����Ñォ�炠�����B�ނ�́A�C���̂����ނ��܂܁A�G�ߕ��̐����܂܁A���ցA���֊C�H�����ǂ�A���R�̉c�݂ɂ܂����A�嗤�̉��ݓ`���ɁA���[�g�s�A�����߂Ĉړ����Â����B������̂͒��N�����̉��݂�쉺���A������̂͗E���ɂ��P�M�𑀂�A�����嗤�]��n�������肩����W�c�ƂȂ��āA�g��I�ɓ��x�ߊC���킽��A�Δn�C���ɕY�������B
�@�Δn�C���ɓn�������ނ�̒蒅�n�́A�쒩�N��k��B�̋�ʂ��Ȃ��A�Δn�C�����n���ƂƂ������ׂ��X�^�C���ł������D���̒n���A���Z�p�E�퐶���y��̍ŏ��ɂ����炳�ꂽ�n�ł���A�����́A�܂��ɓ��{�j�����I�ȓy�n�ł������Ƃ�����B�ނ�́A�Y������������Ղɂ��Ă������A�̏W�S�ʂɂ킽���Ď��n�͖L���s����ŁA���R�̐�����邱�Ƃ����������߁A���R��p�I�����K�v�Ƃ��āB�퐶���������X�ɓ��Ɉڂ��Đ���͔|�����y���A���̌�A�H�Ƃ̕s���͏����������������̂́A��͂茴�n�Y�Ƃł���ȏ�́A�C��E���y�̉e�����ˑR�Ƃ��Ă��т��������B���̂��߁A���R���q�A�R�x�M�ƕ��s���č���i�ĂȂǍ����̂��܂����j�M��������ɍs�Ȃ��Ă����Ǝv����B
�@���̑Δn���n���Ƃ���A����ɑΔn�C���ɂ̂��ĎR�A�n���A�\�o�����ȂǓ��{�C���݂ɑ����̐l�X���n���Ă������B���̎푰�͖k���n�������ł��A�O�q�̃I�z���A���̑��A��l�i�J���g�j���E�A�d�~���E�J�d�~���E�z�{�i�t�Z�j���E�V���i�V���M�j���E����i�R�}�j���E���w�i�A�k�j���ȂǏ\������������Ƃ�����B�������A�Δn�C���ɂ̂��Ă��������̐l�X�̂ق��ɁA�������������͂����葁���A���}���C���i�����j�ɂ���āA���C�B�i�V�x���A�̓���[�j�⒩�N���݂���A�k���푰�Ƃ��̕������Ǝ��̌`�ł����炳��Ă�����������Ȃ��B�Ƃ����̂́A���{�C�̖k������̃��}���C�����A���N�����ɂԂ����ē쉺�A�k�サ�Ă���Δn�C���i�g���ɂԂ��蓌�ɂނ���ς��A���s���邢�͍������Ă₪�Ĕ\�o�����ɒB���邩��ł���B
�@�����̊C����̓n���l�̂��āu�C�l���v�Ƃ������A�ނ�́A�C�݂����łȂ��͐���������̂ڂ�A���̗��������Ђ炢���B�����̊C�l���̂Ȃ��ɂ͏����i��������͏����ɍ������Ă���A�͌��͈�ł������B�j�������̂ڂ����ꑰ�������B
�@�@�@
���H�Ɩ��̂̂��肩���
�@�Y�_��͏���̌Ö��Ƃ��Ă悭�m���Ă���B���݂̏���͏��쒬�Y�_�n����c�f�A���c�i�����s�j�A��咬�𗬂�A�V���s�̘Z�n���ɉ͌��������Ă���B�������A���Ă͂��̐��n�����x���ŁA���쒬�����n�����琼�ɁA���݂̐V�p���i��O�͊ݒi�u�R�j�ɉ����Ĉ�g�E�����E����𗬂�A�Ñ�i����s�j�̖��ցi�݂̂�j������ŁA�����̎嗬�֍������Ă����B��������N�ȏ�O�̒n������ɂ́A��O�i�u��i�����n���E����j�A���i�u��i�|���|����E��������ځj�����삪����Ă������Ƃ����邪�A���Ȃ��Ƃ����i�P�R�N�i�P�S�O�U�j�̍^���ȑO�́A�����_�Еt�߂֗���Ă����Ƃ������L�^������𗧏��Ă���B��̖�K��Ƃ����̂��Â�����̐�ՂƂ����Ă���B�@������ɂ��Ă��A����͂��̕ϑJ�ƂƂ��ɂ��̖��̂��܂��܂��ł������B�̂͗̓y�ӎ��������A���Ƃɕ�������ɂ����Ă͗̓y���قȂ�Α����ł���B���������ĉ͐얼���A�傫����́u���v�ł���A�W���𒆐S�ɂ����ꍇ�A�u�O�̐�v�A�u���̐�v�ƌĂсA�܂��u������v�̂悤�ɁA�n���̏��L�^�ɂ́A���̓y�n�̒n�於�ŌĂ��ꍇ�����������B
�@����͌Â��Y�_��ƌĂ�A�Y�_�_�ЂƐ[���W�ɂ���Ƃ����Ă���B����̖��̂�����ɂ͏������邪�A��ʓI�Ȃ��̂�������ƁA���ÁA�Y�_�_�Ђ𒆐S�ɗY�_�̏��ƌĂ�Ă����B���̊Ԃ𗬂�Ă����̂Łu�Y�_����v�Ƃ���ꂽ�B���ꂪ��ɂȂ��āA�P�Ɂu����v�Ƃ�����悤�ɂȂ������̂Ƃ����B���������āA���̌Ö��̗Y�_����N���͓����ł��낤�B
�@�@��̉c�݂��݂�Ƃ��A��Ƃ͓����͐g��ۂ��̂łȂ��A��J���ƂɋC�܂܂ɕω�������̂ł���B�����Ƃ̍����n�_������ɐ쉺�ւƈړ������A���A�������ӂŁA�Y�_��Ƃ̍����_��n���̂����ł������Ă݂�ƁA�Ñ�̖k���̐����i�����_�������j�␅�q�i�q�͖q��̖q�ł͂Ȃ��A�����t�������ō����_�������j���z�肳���B�����_�͂���ɉ����A���������ӂɂ��ڂ�A����̎嗬���A�����̍��ɂ͒����삩�獂���̐�ې�ւƕς���Ă������B
�@���ƂƂ��ɁA����̗��ꂪ�쉺�։������Ă����o�߂��ӂ肩����ƁA�v�g����͋v�����ԁA�قƂ�Ǐ���̉͏���쌴�ƂȂ��āA�V���̂��Ƃɂ��炳��Ă����̂ł���B����̐삪�Ԗڂ��͂�߂��炵���悤�Ȓ��ɁA���������Ƃ������̐�����B�Ƌu�����������ɂ������B
�@������������̐��������ɒ����������_�̐����Ñ�ɂ����āu�Y�_�́v�A�쉺���u�ː��́v�ƌĂ�ł����B
�@�@
�I�z���̗Y�_��i�o
�@���̍��A�X���n���̕z�����C�i�ӂ��݂̂����݁j�ɂ̓t�Z�����A�ː���͌��t�߂ɂ̓J���g�����Z�݂��Ă������A�I�z���ɂ͂���Ɏː���������̂ڂ��Ă����B
�@����썶�݂̎R�[�̏���s�A�������E�����s��ɂ́A���Ȃ�Â�����蒅���Ă����푰�������炵���A�ꕶ�E�퐶�E�Õ�����̈�Ղ��������邱�Ƃ��������Ă���B��\�I�ȌÕ��Ɏ�{�Õ��E���������Q�i����s�j�E�n�ꉡ���S�E�郖�������S�i�������j�E�]�������Q�i�����s�j���m���Ă��邪�A���n��ōŋ߁i�T�R�N�t�j�A�R�O�O��ȏ㏬�썂�ˌÕ��i�O����~���E��~���E�~���B�����j���������ꂽ�B�]���m���Ă����Õ��́A���̂قƂ�ǂ������Õ��ł��������Ƃ���A�V�����������ꂽ�����̌Õ��ɂ��āA�X�ɏڂ����������҂���Ă���B
�@����A����여��̌Â��n���ɁA�w�I�z���x�̏W�c�����̂���n������B��������ł��łɎ������Ƃ����u�剪���i���Γ��n���j�v�A���̉����ɁA�u�������i���݉E�݂̕������w�����x�ƊW���邩����s��́w���x�������̖��c�肩�B�j�v������B�������̉����ɂ͐ԊہE�O���s���܂ށu��싽�v������A�������������������U�݂��Ă���B�����̒n���͂�������w�I�z���x�̃I�z�������́A���̓]�a�������̂Ǝv����B
�@�܂��A�O�r�̗Y�_��Ə����̍����n�_���Ƃ��������E���q�n���ɗאڂ��ď��_�i�I�R�E�j��������B���̏��_�����w���x�̏ォ��Y�_��̗Y�_�ƂȂ�炩�̊W�����肻���ł���B�Y�_�����_�ƕω����邱�Ƃ͍l�����邱�ƂŁA�Ñ���{�l���A�_�i�J�~�j�Ɣ������ɂ������Ƃ��āA�_�l���J�A�n���ƌĂ悤�ɁA�_���w�J�A�x�Ɣ�������B�Y�_�̔������I�K�~���������\�L���I�K�~���������\�L�ł������ɂ���A�w�I�J�E�x�̓]�a�ł������Ƃ��Ă��ςłȂ��B
�@����s�w�{�ƗR�����x�ɂ��ƁA�����̏��_�i�����j�_���{�́A����̑�×��ŗ���������쒬�̗Y�_�_�Ђ̌�_�̂��܂����̂����[�Ƃ����Ă���B�l�X�͂������т��J�����Y�_���Ɩ��Â��A���̌㏬�_���Ɖ��߂��Ƃ����B�Y�_�_�Ђł����l�̓`���������Ă��邪�A���ɓ`���ł������Ƃ��Ă��A�ނ����̗Y�_��̗�������̂Ƃ�����Ɠ����ɁA�Y�_�M�ɐ[���W������Ǝv����B���쒬�̗Y�_�_�Ђ��͗��̕����_�ɂ������悤�ɁA���̏��_�̒n�������̉͗��̍����_�Ɉʒu���A���̊�_�i�N�i�h�m�J�~���_�b�ɓo�ꂷ��_�j���܂�ɂӂ��킵���n�ł������ł��낤�B�ނ���A���̗Y�_�_�Ђ�����ɐi�o����O�A�Y�_�M�͂����ɂ������̂ł͂Ȃ����B
�@�����Ɛ��_��i�߂�Ȃ�A�u�Y�_�v�́u��_�i�I�z�̐_�j�v���Ȃ킿�A�ː���������̂ڂ����C�l���A�I�z�����܂������_�łȂ��������B�剪��������Ђ炢���I�z���̈�h�́A����ɗY�_��������̂ڂ��ďI���w�̗Y�_�i�o�����̂łȂ��낤���B���̒��Ԓn�_�ɂ͍��팠���i�����炢����j�̈�̂����鍂���M���A���鎞���Ɍ��������̂�������Ȃ��B�����̒n���́A��ʓI�ɐ�̐��̍����Ƃ���Ƃ����Ӗ��������ꂽ�Ƃ����邪�A����ɂ͑嗤�n���l�ł��鍂��i���܁j�l���Z�݂����n�ł���Ƃ����B����̃R�E���C�������ƂȂ����Ƃ����̂ł���B���̒n���ɍ����_�Ɋւ���n���i����—���ܐ�E�J����Ȃǁj�`�����������Ƃ��������Ă���B
�@�@�������ď���i�Y�_��j�������̂ڂ����I�z�����A�ŏ��ɏ��쒬��ɏZ�݂��A��_�i�I�z�_���Y�_�j���܂�A���̎��ӂ�����Ђ炢���B���Ȃ킿�A���́w����тƁx�ƂȂ����̂́A�C�l���ł���I�z���ł������Ƃ����Ȃ����낤���B
�@�ȏ�̂��Ƃ���A���쒬��Ō��݂Ɏc���ԌÂ��n�����u�Y�_�v���邢�́u�Y�_���v�ł���Ƃ�����B�����A�c�O�Ȃ̂́A�������Ă��̒n��i���쒬�Y�_�n���j�ŁA�퐶����E�Õ�����̈�Ղ���������Ă��Ȃ����Ƃł���B�������A�d�m��ԁi�ٓV����̂���Ƃ���j���邢�́A�L�J��̗��悩��A���āA�k��҂��y����̎悵���Ƃ̒m�点�����ꂽ���Ƃ��������B�����́A�y�t��i�͂����j�̗ނŁA�J���̔j�Ђł������B�Y�_�_�Ђ̋��Вn��艜�܂����L�J���Ȃ݂́A���ł͕ޏꐮ�����Ȃ���āA�̂̂��������͂Ȃ����A����ȑO�́A�l�����R�Ɉ͂܂�A���������ɏ������u���݂��A�Ȃ�ƂȂ��Ñ�l�̃��[�g�s�A���������������̂ł������B
�@�Ȃ��A�Y�_���ɂ��Ă݂�ƁA�w�a����i��݂傤���傤�E��������—
�X�R�V�N—���{�e�n�̒n���ȂǕ����̂������W�^���������j�x�ɓv�g�S���i���g�����j�����݂��邪�A�Y�_�͏㗬�n�т̈ꕔ���߂Ă����ɂ���A���̂���ϔO�I���̂ƁA�s���敪�ɂ��ď̂̂Q������������Ă������̂ŁA����̂Ȃ�킵�́A����̐��ڂƂƂ��ɂ�����Ă������Ƃ݂Ă悢�B
�@�ȏ�A�n���ȂǂɁA�I�z���̑������݂Ă������A�ޗǎ���i�V�O�P�N�`�j�́A���̑O�ォ��g��I�ɓn�����Ă����e�푰�ɂ���āA���ꋝ�L�ʁi���܂�Ȃ���g�ɂ��Ă��錾�t�̋��j�͓��{�j�j��ō��������A�܂��ĕ����͌�ɂȂ��Ĕ����ɍ��킹�Ă��ǂ��ǂ������Ă͂߂�ꂽ�L���ł���ȏ�A���Ȃ薳���ȕ����┭�����������ł��낤�B
�y�|�؏~�꒘�@���X�̂�����ƒn�����n���̃��[�c�����쒬�����a�T�S�N��蔲���z