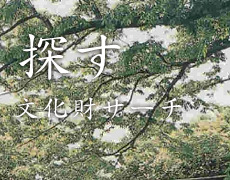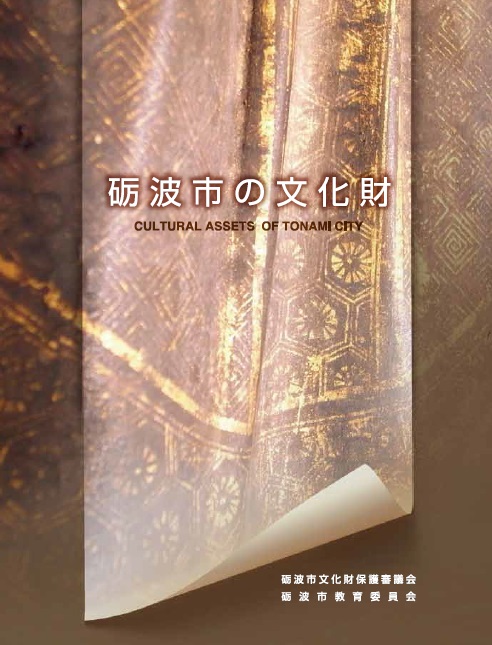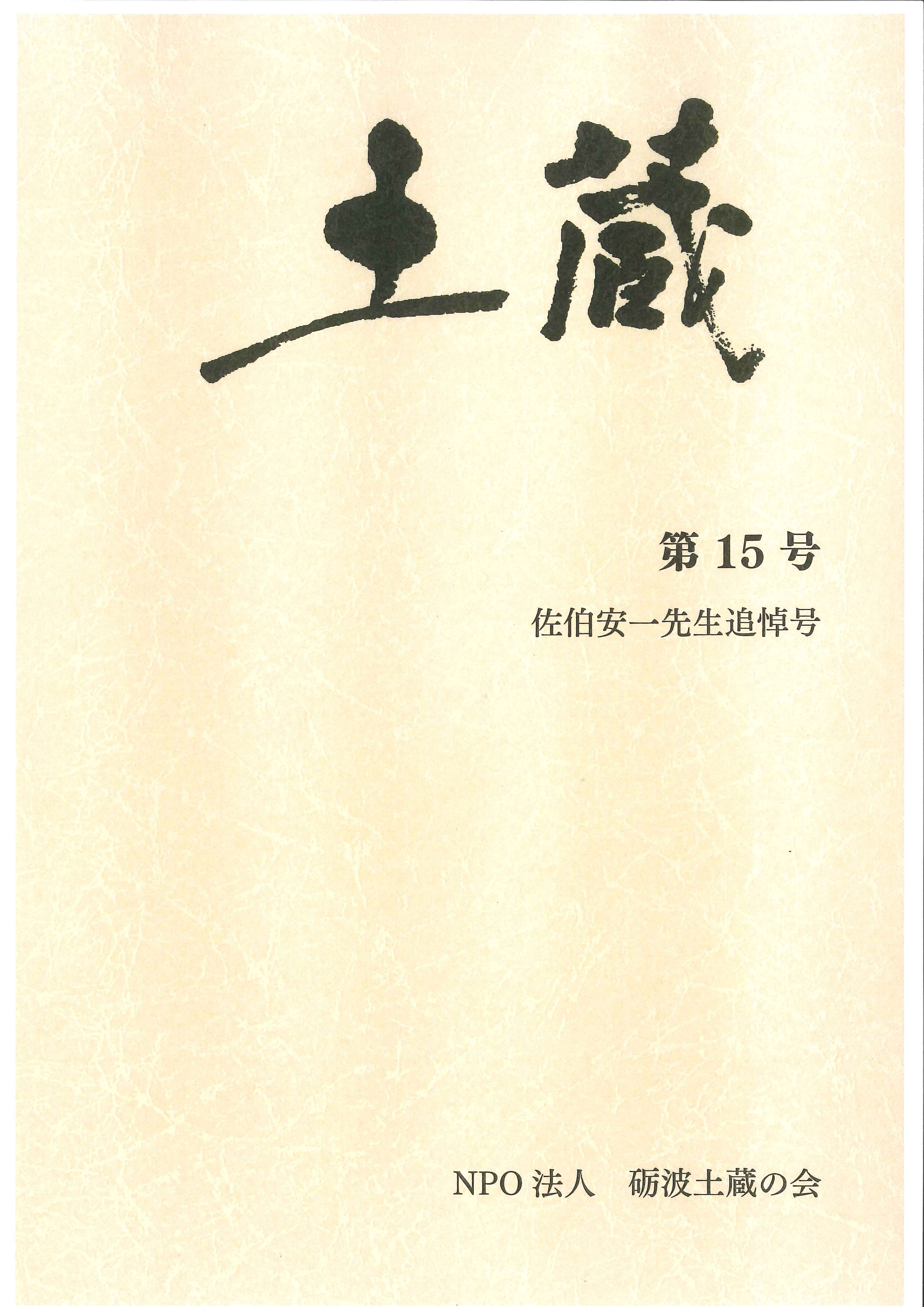松川除堤防と御川除地蔵
2013.3.9
江戸初期、加賀藩が巨費を投じて築いた治水遺産

松川除堤防の終点
松川除堤防と御川除地蔵(まつかわよけていぼうとおんかわよけじぞう)
平成20年2月27日・市指定
砺波市上中野・庄川町青島・庄川町庄(国土交通省他)
松川除堤防は庄川の扇頂部にあります。庄川の治水と砺波平野の開発のために築造され、近世を通じて補強された治水遺跡です。
天正13年(1585)の中部大地震によって、当時千保川を主流としていた庄川は東に新しい川筋を作りました。その後加賀藩は、庄川の治水と砺波平野の開発を進めるため、千保川をはじめ、今まで西方へ流れていた諸分流を締切って、東の新しい川筋(現庄川)へ一本化する工事を始めました。工事は寛文10年(1670)に始まり、正徳4年(1714)に完成、工事費は藩の御納戸金と流域村からの水下銀によって賄いました。
堤防工事の歴史

航空写真
しかし、大出水の際、しばしば切れたので補強、盛足し工事は幕末に至るまで続けられました。文化4年(1807)に根固めのため松が植えられたので、地元では 松川除と呼びました。この呼び名は現在でも使われています。
長さ八百五十間(1,530m)といわれます。
現在は中野発電所横の堤防となっており、現在県道高岡庄川線が通っています。また、松川除の呼称の初見は天保5 年(1834)(菊池文書)で、文化4年の松植栽より27年後です。
先人の知恵 霞堤のシステム

かつての鷹栖用水取入口付近の様子(庄川町史より)
松川除の松は戦時中に伐られましたが、前堰の松は残っているので、かつての松川除の景観を偲ぶことができます。また両堤防を総合して「霞堤」のシステムを残しています。霞堤とは、上流側と下流側の堤防が二重になるような不連続な堤防のこと。洪水時に堤内地に水を貯めることができるのです。
堤防の安泰を願って

御川除地蔵
御川除地蔵は、年記はありませんが古様な阿弥陀坐像で、台石に「御川除」と刻まれています。松川除の安泰を願って造立されたと考えられます。
- アクセス
- 砺波ICから車で20分